釣果
ヒラメとは?ヒラメの生態
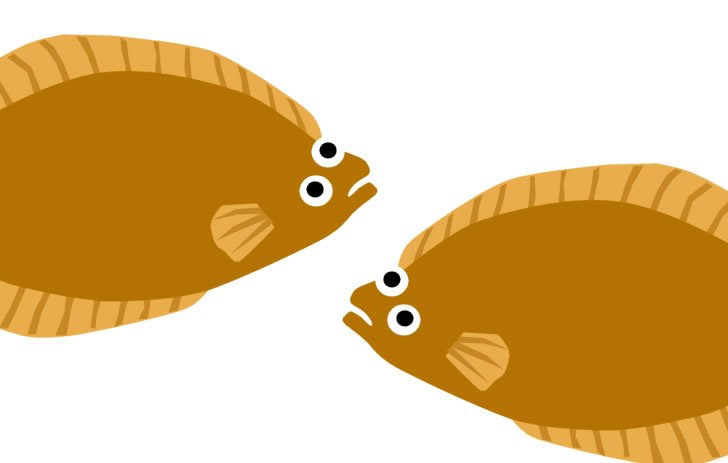
ヒラメの生態
最大で全長1m、体重10kg以上にもなる
オスが最大60cm程度なのに対してメスは最大で1m以上にもなる
世界最大のヒラメは神奈川県の大磯海岸釣られたで1m5mm、重さ10kg
左向きがヒラメで右向きがカレイ(左ヒラメ右カレイ)
歯が鋭く基本的には生きたベイト(小魚)・甲殻類(カニ)・ゴガイなどを捕食する
昼は泥の中に身を潜めベイトを狙っている
活性が高い場合がは砂に潜らず上を通るベイト積極的に追いかける
カメレオン同様、砂の色に合わせて体の色を変化させられる
3月~7月(九州南部では1月から3月、本州で2月から6月、北海道では6月から8月)が産卵期。産卵する個体の多くは体調50cm以上とも言われている
そのため産卵期にサーフから釣れるのは50cm未満であることが多い
羽化したばかりの稚魚はイナダやシーバスなどと同じ様に体の両方に目がある
30cm未満のヒラメはソゲと呼ばれている。(人によっては40cm未満または1kg以下をソゲと呼ぶ場合もある)
80cm以上をランカーヒラメ呼ぶ(7~8年)
3年でオスが40cm、メスで50cm近くまで成長する
寿命は数年。カレイは数十年
主に砂地に生息しているが磯などにも多く生息する
生物分類学上はスズキ系カレイ目カレイ亜目ヒラメ科ヒラメ属
欧米ではflatfish(フラットフィッシュ)またはflounder(フラウンダー)と呼ばれている。ちなみにカレイも同様の呼び名で特に区別はしていないようだ
ヒラメの身は左右で大きさと質、が違い。味も違うと言われている
春の産卵期に向けて栄養を蓄えるので冬が一番うまいと言われている冬に取れるヒラメは寒ビラメと言われている
回転寿司で出されるエンガワの多くはカラス鰈(カラスカレイ)と言われている
天然のヒラメの裏側は真っ白なのに対して養殖物は裏側に黒い斑点が見られる
朝まずめ、夕まずめに活発的に捕食活動を行う
夜行性のため日が沈んだ後も積極的に捕食活動を行う
基本的は夜行性と言われているが日中でも捕食活動を行う
獰猛な性格でベイトを積極的に襲う。またかなりしつこい性格のため追い食い(取り損ねたベイトを再度追いかけて捕食すること)することも多いと言われている
ヒラメの漁獲量日本一は青森県(1,339t)、続いて北海道、福島県、茨城県、新潟県の順
※平成22年調べ
水深50cm~100mまでの生息している
捕食が決してうまい魚と言えないが、頭上を通る魚に食いつく際は全身を使い俊敏に捕食する
淡水を好まないと言われているが河口付近は絶好のポイントであることや河口内でも良型のヒラメが釣れる場合がある
マゴチと同じように海底に生息しているが捕食のために海面までベイトを追いかけてくることがある
青森県・岩手県・鳥取県の県魚はヒラメ
捕食のために水面からジャンプする場合もある
その他おすすめのコンテンツ一覧
-

河川でシーバスが釣れるポイント
-

生き餌のつけ方(泳がせ釣り)
-

夜のナイトゲームでのアオリイカの釣り方(エギング)
-

夏のシーバス攻略
-

ルアーの飛距離を伸ばし遠投する30の方法
-

シーバスが釣れる時合い(時間とタイミング)
-

サーフでヒラメの釣れる12のポイント
-

秋のシーバス攻略
-

コノシロパターンのシーバス攻略
-

サーフでバラさないためのやり取りとランディング方法
-

ヒラメ釣りで使われるルアーの種類16選
-

平砂浦海岸(千葉県南房総市)
-

ビックベイトでのシーバス攻略の基本
-

バチ抜けパターンのシーバス攻略
-

夏のヒラスズキ攻略
-

最近のヒラメ用メタルジグは!?ヒラメ用メタルジグ全18選
-

ルアーフィッシングでスナップを使うメリットとデメリット
-

パイロットルアーとは?パイロットルアーに適したルアーは?
-

春のヒラスズキ攻略
-

ランディングネットの基本と選び方
-

ランディングネット(タモ網)の使い方
-

春夏秋冬と季節別のマゴチ釣り
-

ヒラメ・マゴチの釣り方を大久保亨一氏の動画から学ぶ
-

前原海岸海水浴場(千葉県鴨川市)
























