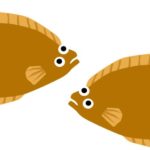釣果
冬のヒラメ釣りとルアー選択

冬のヒラメの釣り方
冬のヒラメの特徴
ヒラメの適水温は18度~20度前後と言われている。そのため冬になるとほとんどのヒラメは水温の安定している深場へと移動してしまう。しかし中にはベイトの接岸に合わせて浅場へと寄ってくるヒラメや浅場に残るヒラメもいる。
特にそう言った個体はサイズが大きいため、冬は数こそでないものの大きいサイズが釣れやすいと言った特徴がある。
冬こそ夕マズメの時合いが熱い
上記でも記載したように冬は水温が低下するためヒラメの接岸が減る時期。そんな中でも夕マズメは日中、陽の光で水温が上がり時合いとなる可能性が高い。特に遠浅サーフは水深がないため陽の出ている時間が短くなる冬でもしっかりと水温が上昇することが多い。もちろん適水温まで上昇することは少ないが朝マズメよりも水温上がりヒラメにとっては良い環境となりやすい。
冬でも朝マズメはベイトが動き出す時間帯であるためヒラメも接岸し活性が上がりやすいので朝マズメも忘れずにエントリーしておきたいが、夕マズメはサーフにエントリーするアングラーの数も朝マズメより減る傾向いあるため朝よりも多くのポイントを広範囲に攻めることが可能だ。
冬にヒラメが釣れやすい場所
根の多いサーフや磯
繰り返しになってしまうが、冬は水温の低下と日照時間の短縮によりベイトの餌となるプランクトンが発生しにくいため、多くのベイトが沖にでてしまいサーフには魚が少なくなる。しかしそういった冬の時期でも磯には小魚が多く残る。また、カサゴ(ガシラ)やソイなど根魚は冬もハイシーズンとなるため根の多い場所には活性の高い根魚が数多くいる。
つまり磯はもちろん、根の多いサーフやゴロタ浜ではそういったベイトを狙いヒラメが接岸している可能性が高い。
河口付近
川から流れる水は海水温よりも高いことが多い。そのため河口付近はもちろん、小さい川でも海に水が流れ込んでいる場所は水温が高くなりやすく、ヒラメが接岸している可能性も高い。
特に大きな河口は水温が上昇している範囲も広いためヒラメの数も多くなりやすい。ただし潮の流れによって河口の左右で水温が高い方と低い方が別れる。潮の流れを掴みどちらの水温が上昇しているかをうまく判断すれば他のアングラーよりもヒラメの釣れるチャンスは大きくなる。
冬のヒラメがメインにしているベイト
先程も記載したが冬はベイトが少ない時期。しかしまったくいないわけではない。ここでは冬にヒラメのメインベイトとなる魚を紹介していく。
コノシロ
冬と言えばコノシロ。コノシロは20cm~30cm前後とベイトの中でも比較的サイズが大きい。そのためコノシロを捕食できるヒラメも必然的に大きくなる。コノシロの群れの下には大型のヒラメがついている可能性が高い。
ヒイラギ
ヒイラギは年中どこにでもいる魚だがベイトが減った冬には代表的なベイトとなる。特に波の静かな浅瀬を好むためヒラメがヒイラギにつけば足元まで接岸してくる可能性もある。
また、ヒイラギは夜になると波の穏やかな漁港内に入ってくることが多い。そのため漁港が近くにあるサーフにはヒラメがいる可能性が高い。
ヒイラギがいる時はバイブレーションがおすすめだ。バイブレーションはヒイラギの形に似ているだけでなく、活性の低いヒラメにも波動でアピールすることができるので捕食スイッチを入れやすい。
冬のおすすめヒラメルアー
ワーム
基本的に深場にいることが多くなるこの時期は接岸してくる個体がいるとはいえ春や秋ほど活性は高くない。
そんな活性の低いヒラメに効果的なのがワームだ。ワームでボトム付近を丹念に攻めると同時にヒラメの目の前にワームを通してやることで活性の低いヒラメでもバイトを誘うことができる。
また、コノシロを除けば表層付近を泳ぐベイトは基本的にいない。そのため表層付近を攻めやすいミノーなどよりもボトム付近を攻めやすいワームに結果が出やすい。
ナチュラルカラーのミノー
冬の太平洋側のサーフの特徴と言えば透明度の高さ。冬は北西からの風が吹くため濁りがでても風の影響で濁りが取れやすい。また、プランクトンが発生しにくいため、プランクトンによる濁りもでにくい。そのためヒラメも視界も良くなるので比較的ナチュラルなカラーでも遠くのヒラメにアピールすることが可能だ。
冬はルアーをゆっくりと泳がせる
朝マズメや夕マズメは冬であってもヒラメの活性が高くなるためルアーを早く動かしてもバイトしてくる可能性が高い。
しかし、春や秋などのハイシーズンと比べてしまうと活性の高いヒラメが多いとは言えない。
そのため、活性の低いヒラメでもバイトがしやすいようにゆっくり引けるルアーが有効になってくることが多い。フローティングミノーはもちろんのこと、ヘビーシンキングミノーよりもシンキングミノーなど比重の軽いルアーであれば底を引きずらずにルアーをゆっくりと泳がせることができる。特に遠浅サーフなどでは遠投するため比重の重いルアーを使用することが多いが冬には遠投だけでなくゆっくりと泳がせることも攻略方法となる場合が多い。
もちろん、比重の重いヘビーシンキングミノーやメタルジグが釣れないという訳ではない。あくまでも冬のヒラメに合わせたリトリーブを意思しルアーローテーションしていくことで他のアングラーが拾いきれていない寒鮃を釣っていくことが可能となる。
ただし注意は必要だ。サーフでの釣りは波の影響を大きく受ける。波がある状況でゆっくりルアーを動かしてしまうと波の影響でラインスラッグが多く出てしまい、ヒラメのアタリに気づくことができない。
また、フローティングミノーは波の高い日などは波の影響で水面から飛び出してしまったり、うまくアクションしてくれないことが多い。さらに、フローティングミノーはもちろん比較的比重の軽いシンキングミノーなどは風などが強い日はヒラメのいる場所まで遠投できない可能性もある。その日の状況に合わせてルアー選択をすることやリトリーブスピードを変更することが大切だ。
サーフにいる冬のヒラメは大きなベイトを捕食していることが多い
上記でも説明したように冬に残っているベイトは比較的大型なことが多い。また、春に数センチだったボラの稚魚であるハクも冬になると20cm弱程度まで成長している。もちろんボラだけでなくその他のベイトも冬になるとある程度の大きさまでに成長している。そのため冬は比較的大きなサイズのルアーに反応しやすい。
さらに魚は大型であるほど寒さに強い。それはヒラメにも同様のことが言え、冬の低水温期にサーフから狙える範囲まで接岸してくる個体はある程度大きな個体であることが多く、比較的大きなサイズのルアーでも難なく捕食することができる。
その時に接岸しているベイトが小さければ大きなルアーへの反応も悪くなることがあるが、コノシロやイナッコなど20cm前後のベイトが多いようであれば大きなルアーで広範囲にアピールすることで効率よく冬のヒラメを攻略することができる。
その他のシーズンの釣り方
その他おすすめのコンテンツ一覧
-

ヒラスズキの基本的な釣り方とコツ
-

サーフでのシーバスフィッシングの基礎
-

ナイロン、エステル、フロロ、PEラインの違い
-

ヒラメとは?ヒラメの生態
-

離岸流の見つけ方
-

釣りの種類11選
-

港湾でシーバスの釣れる11のポイント
-

ルアーをただ巻きすることの重要性
-

メタルジグの種類
-

ハイギアリールとローギアリールのメリット
-

平砂浦海岸(千葉県南房総市)
-

濁りがある時のヒラメの釣り方
-

春のシーバス攻略
-

サーフとゴロタ浜のエギングのポイント
-

サーフからのヒラメの釣り方を堀田光哉から学べる動画
-

川上靖雄さん流のシーバスの釣り方を学べる動画
-

シーバスの釣れるワームの基本
-

ハゼパターンのシーバス攻略
-

大島英明氏によるヒラメの釣り方動画
-

サーフでヒラメが釣れない人の18の特徴
-

ボートシーバス(オフショア)をプロのアングラーから学べる動画
-

夏にアオリイカをエギングで釣る方法
-

アオリイカをサイトフィッシングで釣るコツ(サイトエギング)
-

ヒラメやマゴチ釣りでよく使われる7つのルアーアクション